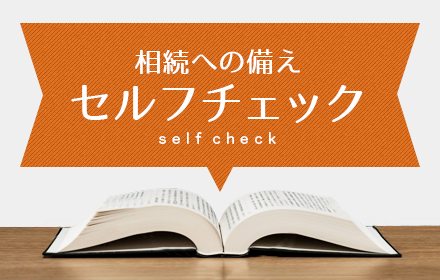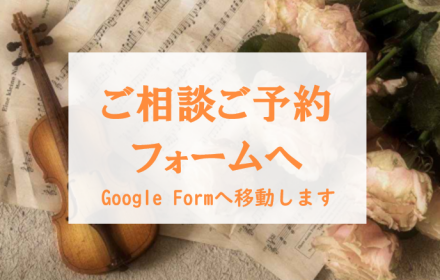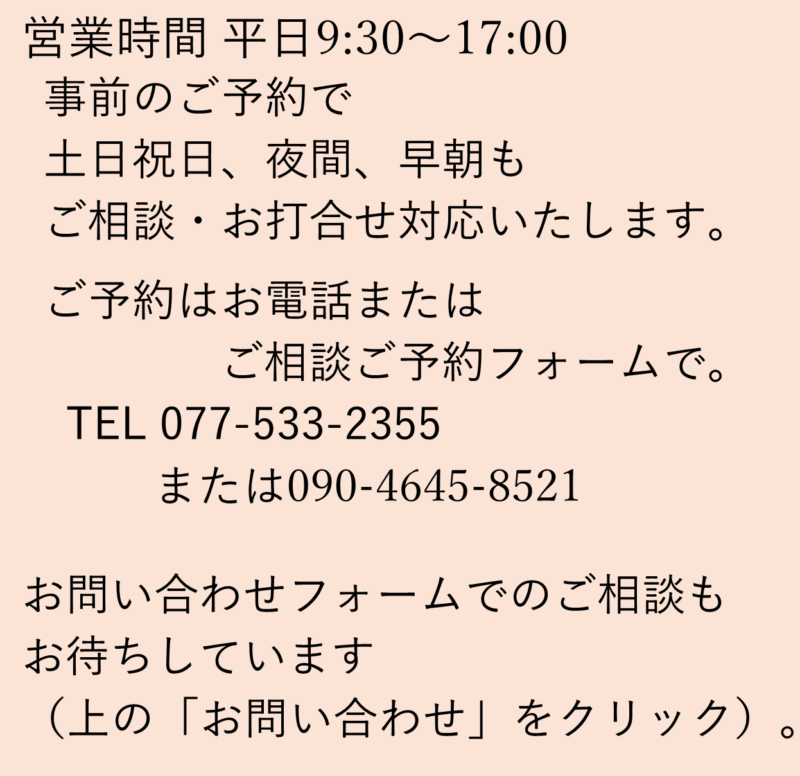ここで出てくるキーワード
遺言書:自分の財産を誰にどれだけ相続させたいかを、自分がまだ判断能力があるうちに書いておく書面のこと。
種類として、「自筆証書遺言書」「公正証書遺言書」「秘密証書遺言書」などあり、前者2つがよく使われます。
相続分を遺言書で指定すれば、法的効力が生じます。
遺産分割:相続が発生し、遺言書がない場合は法定相続人全員で遺産分割について協議をします。その結果を書面にしたものが
遺産分割協議書です。
遺言書がない場合、遺産分割に関する亡くなった人の意思がわからないので、法定相続人全員が話し合いをして相続分や相続の方法について決める必要があります。遺産分割協議書は相続手続きに必要となる書類です。
どんな準備が必要か、ケースに当てはまることが自分にはないか、ここで検証していただけたらと思います。
相続人の一人に多く遺したい |
|---|
|
例えば、子供が数人いたとして、そのなかの一人に他の子供より多く遺したいという場合、遺言書で事前に準備しておくことをお勧めします。 具体的な例として、 ・会社を一人の子供に継いでもらいたい ・子供の一人の面倒を他の子どもに見たもらいたいから、その子に現金を多めに遺して資金を備えたい ・世話になった長女に多く遺したい など、理由はさまざまですが、普段からご家族で話をしたり遺言書で準備をして、相続が起きてからの手続が円滑に進むように備えることをおすすめします。 |
子供がいない |
|
・子供が先に亡くなっている場合は、孫がいればその孫が相続人になります。 ・子供も孫もいない場合は、相続人は配偶者と親か兄弟姉妹になります。 ・子供が相続を放棄した場合は、孫は相続人にはなりません。 相続が起きたとして、例えば相続人が配偶者と親や兄弟姉妹であった場合には、配偶者と親又は兄弟姉妹が遺産分割についての話し合いをしなければなりません。配偶者にとってはそのような話し合いは精神的に負担となるかもしれませんので、その負担を少しでも軽減するために遺言書で準備をしておくことをおすすめします。 |
再婚しているが、前の配偶者との間に子供がいる |
|
前の配偶者との間の子供も相続人です。相続させたい場合させたくない場合、どちらの場合も遺言書や生前贈与などで備えておくことをおすすめします。 例えば、 ・相続が起こると、相続手続きのためには亡くなった人が遺した遺言書か遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書は、法定相続人全員が話し合って相続の内容を決めて作成しなければなりません。前の配偶者との子供と現在の配偶者や子供が仲が良いという状態であれば心配ご無用かもしれませんが、面識がなかったり仲が良くない場合、遺産分割の話し合いをしなければならないのは酷といえます。遺言書での備えで、そのような状況を防げます。 ・また、前の配偶者との間の子供が未成年であれば、前の配偶者が代理人として遺産分割協議に参加することになります。遺言書があればそのような協議は必要なく相続手続が進められます。 |
誰にも相続させたくない |
|
・相続人となる者はいるが誰にも相続させたくないといった場合であっても、遺言書がなければ法定相続人が相続することになります。 ・法定相続人を廃除することができます。 例えば、相続人に暴力を振るわれたり屈辱的な目に遭わされるなど、その相続人を相続人から排除したい場合には、家庭裁判所にその旨請求することができます(民法892条)。また、遺言書によっても廃除することができます。また、この廃除の請求は本人(被相続人)がいつでも取り消すことができます(民法894条)。 |
相続人がいない |
|
・唯一相続人となる者はいるが、その人が相続人となる資格がない場合には、相続人がいない場合に該当します。相続人となる資格がない場合とは、民法891条の相続人の欠格事由に該当することをいい、例えば自分が相続人になるために他の相続人を死なせたり、詐欺や強迫により遺言書を書かせたり、遺言書を隠したりすると相続人になることができなくなります。 ・相続人全員が相続放棄をした場合も、相続人がいない場合にあてはまります。 相続人となる者がいない場合には、遺言書がなければ利害関係者や検察官の申し立てにより家庭裁判所において手続が進み、特別縁故者(内縁の妻や事実上の親子など)がいた場合に引き渡しが済んでなお残った財産は、国庫に帰属します。 遺言書があれば、内縁の妻や事実上の親子その他のお世話になった方や介護をしてくれた方、団体への寄付などをすることができます。 |
ブログを開設している、アフィリエイトである |
|
ネット上でブログを書いている場合、無料であれば特に慌ててアカウントを削除するといった必要はないと思われます。が、サーバーレンタルに料金がかかっていたり、ドメインを取得していて自動更新されているといった場合には、放置しておくと料金が発生するので、対策が必要となります。自分で手続きできればいいですが、それができなくなる事態がいつ訪れるかわからないので、エンディングノートを利用して有料の場合に請求メールが届くメールアドレスを書いておいたり、契約先やアカウントの情報を書いておくなどしておくと、残されたご家族に解約してもらえます。ご家族にメールの内容やブログを読まれるのが恥ずかしいという場合には、わたしがお手伝いしますのでご相談ください。 |
一人暮らし、頼れる親族がいない。 |
|
・財産を誰かに遺したいとき 財産を誰かに遺したいのであれば、遺言書を書くことをおすすめします。 ・将来の後見人の事前準備 何も準備をしていなければ、将来、もしも認知症などで判断能力が低下したとき、自分の知らない人が後見人になるかもしれませんが、事前に任意後見契約をしておくことで、自分が選んだ人に後見人になってもらうことができます。相手は家族や親せきの方、友人、行政書士や弁護士、司法書士などでもいいのです。 任意後見契約書にどんなことを代理してほしいかを盛り込むことができますし、確実にこうしてほしいと決まっているわけではないが希望がある、という場合にはライフプランを作っておくこともできます。契約書の作成、お手伝いします。準備しないままに法定後見を利用することになった場合、自分の希望を叶えることは難しくなります。 任意後見契約は公正証書にしなければなりません。費用はかかりますが、法定後見に比べると任意後見は自分らしい生活が送れると思います。 ・判断能力が低下するまでの間のこと 任意後見契約を締結しても、判断能力がしっかりしている間は任意後見は始まりません。 判断能力が低下し申立てにより任意後見監督人が選任されて始まります。 それまでの間、判断能力が低下していないか見守ってもらうことができます(見守り契約 任意後見契約とは別の契約です)。月に2度は電話で話す、一緒に散歩する、毎週メールでやり取りする、といったふうに、好きな頻度、方法で見守りを委任することができます。 また、銀行に行くことが困難になってきた、家賃収入の管理をしてほしい、といったときは、財産管理契約を結んでおくことができます(財産管理等委任契約)。 ・亡くなったあとの事務処理 死後事務委任契約を締結して、誰かに亡くなったあとの事務をしてもらうよう依頼しておくことができます。 |
随時更新いたします。